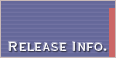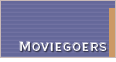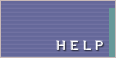| |
|
 第3話 「RONIN」を深く味わうための「決めセリフ」 第3話 「RONIN」を深く味わうための「決めセリフ」 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
ストーリー:
タイトルの「RONIN」とは、国を捨て従うべき主人なく、ただ金の為に戦う、ズバリ「浪人」。この映画に登場するのは東西冷戦時代に活躍した、爆弾・武器などの専門を持つ元諜報員たち。ロバート・デ・ニーロ演じるサムとジャン・レノ演じるビンセントがその一団を率いる。
この映画では、要所要所でRONINたちのピリっとした「決めセリフ」が出てくるのに注目してください。これなくしてはこの映画は引き締まりません。また、米国版DVD収録のオーディオコメンタリーでは、フランケンハイマー監督が、細かいカットの説明などこの映画に対する深い思い入れをじっくり語り聞かせてくれます。監督がわかりやすく話してくれますので、米国版DVDを手に入れたらコメンタリー鑑賞にもチャレンジしてみよう!
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
Clipping 1: |
RONIN・Samの決めゼリフ・その1 |
|
|
| |
|
|
冒頭のシーン。雨の夜、パリのバーに集合した男たちは、裏口から次々とバンに乗り込む。サム(ロバート・デニーロ)がボトルケースの下に隠しておいた銃を取り出す。
| Deiedre: |
What were you doing here? |
|
さっきここで何していたの? |
| Sam: |
Lady, I never walk into a place I don't know how to walk out. |
|
出口がわからない所には入らない主義だ。 |
| Deiedre: |
Then why would he get into that van? |
|
じゃぁなぜこのバンに乗り込むのかしら? |
| Sam: |
You know the reason. |
|
それはわかってるだろう。 |
"I never walk into a place I don't know how to walk out."
"walk into"(~に入ってゆく)と "walk
out" (~から出ていく)という正反対の言葉を使った、語感のいいセリフ。否定に "don't" ではなく "never" を使い、文をやや強めています。"I
don't know how to walk out" が 直前の "a place" を修飾。"a
place I don't know how to walk out" で「出口がわからない場所」。
逃走経路を必ず確かめるという、サムの仕事ぶりがよく出ています。さすが元CIA!
|
コメンタリー裏話:このセリフは、冒頭でRONINたちが集合するパリのバーでのシーンから。パリに長いこと住んだフランケンハイマー監督は、雨の降る寒いパリを最初のシーンにぜひ使いたかったそうです。ここでは、撮影用セットのパブ店内と、ロケをした建物の周囲とが、ちぐはぐにならないよう工夫したカット編集となっています。デ・ニーロ扮するサムがしばらくパブの中の様子を伺い、銃を隠すシーンによって、この男が注意深く、仕事のプロであることを示したかったとフランケンハイマー監督。 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
Clipping
2: |
RONIN・Vincentの決めゼリフ |
|
|
| |
|
|
今夜の宿に到着したRONINたちは、食事をしながらぽつりぽつりと会話を始める。
| Vincent: |
Seven fat years and seven lean years. |
|
いい時が7年、悪い時が7年。 |
| Sam: |
That's what it says in the Bible. |
|
聖書のとおりだな。 |
| Spencer: |
You ever kill anybody? |
|
人を殺したことあるか? |
| Sam: |
I hurt someone's feelings once. |
|
いちど人の気持ちを傷つけたことがある。 |
| Spencer: |
Don't I know you? |
|
前に会ったかな? |
| Sam: |
I don't think so. I'd remember. |
|
いや、覚えがない。 |
"Seven fat
years and seven lean years."
これは、聖書に書かれているヨセフのエピソードを引用したものです。聖書にあまり馴染みのない日本人にはわかりにくいはず。そこでヨセフのエピソードについて説明しましょう。
ヨセフはヤコブの第11子で、ヤコブに偏愛されたため兄たちによって投獄されてしまいます。しかし、ヨセフには夢判断をする能力がありました。ある日、「7匹の肥えた牛と7匹の痩せた牛、実のぎっしり詰まった7本のとうもろこしと、実のない7本のとうもろこし」の夢を見たファラオ(王)は、ヨセフにこの夢の意味を尋ねます。ヨセフは、「これから豊作が7年あり、その後に飢饉が7年続くでしょう」と予言し、それが見事に的中したため、ヨセフはエジプトの宰相となるという話です。
"Seven
fat years" は、現在、経済用語にもなっており、アメリカの1983年から1990年の好景気のことを指します。ここではジャン・レノ扮するビンセントが、彼らが活躍した冷戦中と、用済みとなった冷戦後のことを指して、「いい時期の後に、悪い時期が続く。」と例えています。
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
Clipping
3: |
監督お気に入りの名言 |
|
|
| |
|
|
いよいよ作戦を開始したRONINたち。しかし、仲間の一人、グレッグがケースを持って逃走してしまう。グレッグの行方を探すため、サムは、元同僚に助けを求める。
| Vincent: |
A
friend of yours? |
|
友達か? |
| Sam: |
Yeah,
we went to high school together. |
|
高校時代の同級生だ。 |
| Vincent: |
Everyone's
your brother until the rent comes due. |
|
まぁ、金がからむまでは皆おだやかだな。 |
| Sam: |
Ain't
it the truth? |
|
全くだ。 |
"Everyone's your brother until the rent comes due."
直訳すると、「家賃の支払期限が来るまでは、誰もがみな兄弟だ。」ここで "the
rent comes" と "come" を使っていることに注意。日本語の「来る」と同様、時間の経過の時にも使えるんですね。"due" は「支払期限」。
|
コメンタリー裏話:これは、フランケンハイマー監督のお気に入りセリフだそう。「全くこのとおりだよ」とも。 |
|
"Everyone's
your brother until the rent comes due."
ここでのサムの言葉にも注目!"ain't" は、(she) "isn't"、(you)
"aren't " など否定のbe動詞をすべて "ain't" にできてしまう不思議なスラングです。ハリウッド映画の最重要スラングの一つ!
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
Clipping
4: |
RONIN・Samの決めぜりふ・その2 |
|
|
| |
|
|
サムとビンセントが車の中でディエドラらを待ち伏せするシーン。
| Vincent: |
Under
the bridge by the river, how did you know it was an ambush? |
|
川辺の橋のところで、待ち伏せがいるってなぜわかった? |
| Sam: |
Whenever
there is any doubt, there is no doubt. |
|
あやしいときってのは、いつも間違いなく危険がある。 |
| |
That's
the first thing they teach you. |
|
まず初めに教わることだ。 |
| Vincent: |
Who taught
you? |
|
誰に教えてもらった? |
| Sam: |
I don't
remember. |
|
覚えていない。 |
| |
That's
the second thing they teach you.
(ディエドラらが建物から出てくる) |
|
二番目には教わるのは忘れることだ。 |
| |
All
good things come to those who wait. |
|
待っている者には幸運はやってくる。 |
キーワード "ambush" =「待ち伏せ」
何度となく出てくるこの "ambush" という言葉は、この映画のキーワードのひとつです!このシーン以外でも、ケースを盗みだす作戦を練っているシーンで、サムがコーヒーカップを "ambush" に見立ててスペンス(ショーン・ビーン)を試す場面
があります。そこで、サム曰く、"I ambushed you with a cup of coffee."
|
コメンタリー裏話:橋の下での"ambush"のシーンでは、激しい撃ち合いに発展します。実は、住民への配慮から、パリでは映画撮影に銃を使ってはいけないきまりがあるそう。しかし、この「RONIN」の撮影では特別許可が出ました。ハリウッド映画でパリが舞台になるケースは少なく、この作品で少々パリを宣伝し、これからもパリで撮影をしてもらおうという狙いがあったとか。 |
|
"Whenever there is any doubt, there is no doubt."
一見、きつねにつままれたような、このセリフ。「疑わしい時はいつも疑いがない。」つまり、「疑わしい」事というのは、「疑わしいのではなく、実際にその通りになるのだ」ということ。さすが、やり手のセリフですね。
"All
good things come to those who wait."
これは昔から言われていることわざ。車の中で待ち伏せていると、ディエドラ(ナターシャ・マケルホーン)らが、様子を伺いつつ建物から出てきたところでのサムの一言。今でも日常に使われていることわざです。辛抱強く待っていたら、いいことがあった!という時にさりげなく使ってみましょう。
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
Clipping
5: |
大迫力のカー・レース!! |
|
|
| |
|
|
ものすごい緊張感とスピード感のカー・レースはこの映画の一番の見どころ!リアリズムの巨匠とも言われるフランケンハイマー監督曰く、"Nothing is fake!"
|
コメンタリー裏話:まずはニースを舞台に迫力いっぱいのカー・アクション。狭いニースの路地を猛スピードで走り抜けます!この迫力は、カメラワークによるテクニックではなく、実際にあのスピードで走行しての撮影。監督自身も撮影中は車の中にいたというのだからすごい。街を抜け、山道に出たところでデ・ニーロがロケットランチャーをぶっぱなし、前方の車が炎を出して転倒するシーン、覚えていますか?何と炎上した車の中には、実際にスタントドライバーが乗っており、自分で爆発ボタンを押したそうです!
後半、今度はパリで再びカー・レースのシーン。ここでは、デ・ニーロ自身がかなりの部分で実際にハンドルを握りました。また、右ハンドル車を利用し、右側の運転席にはスタントドライバー、助手席には偽のハンドルを握った出演者を座らせ、実際に運転しているようしたカットも。トンネルに入る直前、デ・ニーロが乗ったプジョーがカーブを曲がるシーンでは、「いままでこんなにすごい四輪ドリフトを見たことがない!!」と監督も興奮しまくって話しています。このシーンのドライバーは、F-1レーサーのJean-Pierre
Jarrier。トンネル内ではひっくり返るパトカーがありますが、ここでもまた車中にはスタントマンがいます!反対車線を走る抜けるシーンでは、スタントマンが周囲のすべての車を運転、そのスタントドライバーの数は300人という大がかりの撮影でした。 |
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |